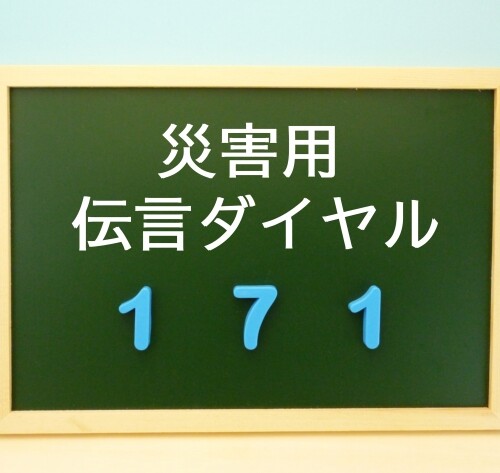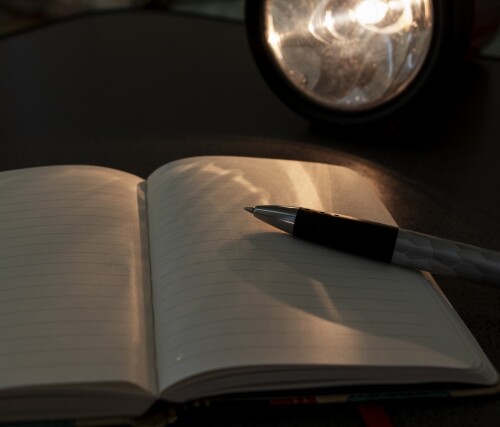避難所か自宅(職場)か、マイタイムラインに応じた避難計画を

かつては「災害が発生した時は、非常持ち出し袋を背負って避難所に行く」という一律の行動原理が推奨されておりましたが、実態はお年寄りなど限られた人だけが避難して、仕事など日々の生活を優先してギリギリまで避難しない人も多かった例があります。さらに大きな災害の場合には、ほとんどの人が避難所に避難して物資が不足したり、肩を寄せ合うくらいの混雑具合になることもありました。
このような事態になる背景の一因には、どのタイミングで避難すれば良いか、この状況で避難した方がいいのかどうか、という判断ができない、遅れるということがあります。判断できない理由には、自宅(職場)の災害リスクを正しく把握していない、自宅(職場)の安全(危険)性を把握していない、十分な対策、備えをしていなかったなどがあります。
しかし、自宅(職場)のリスク判断や適切な備え、準備をするのは大変な作業です。そこでポイントになるのが「マイタイムライン」です。
マイタイムラインとは、住民一人ひとりのタイムライン(防災行動計画)であり、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理し、自ら考え命を守る避難行動のための一助とするものです。
それぞれの災害リスクに応じた事前の備えと行動指針、予備プランを計画することで、適切なタイミングでの避難や、場合によっては避難所を使用しない避難生活を送ることも可能です。
1.まずは大方針を定める。

災害に遭う場所が、自宅(職場)や自宅(職場)に近い場所なのか、どのような災害に遭うのか、様々なケースが考えられますが、最初のステップとしては、身の安全を確保した後で、自宅(職場)で避難するのか、避難所に行くのか、それとも安全なエリアまで移動するのかなどの大方針を定めます。
地震なのか、水害なのか災害の種類にもよりますが、自宅(職場)が無事であれば、避難所に行かなくても良いかもしれません。逆に、万全な備えをしてても建物が全壊していれば自宅(職場)での避難は難しいですし、広範囲に被害が出ていると避難所も使用できない場合があります。
2.バックアッププランを用意する。

定めた大方針に沿って行動できればいいですが、予想外の事態があるなどで定めた方針に沿って行動できない場合があります。そういった場合に備えて予備のプラン、バックアッププランも用意しておくと慌てずに済みます。
例えば、怪我を負うなど体調が万全でない場合や、避難所に向かったがかなり混雑していて入れそうになかったなど、取り決めておいた想定が崩れる場合もあります。そんな時に事前の策としてどうするのかを定めておけば、その想定の範囲内であれば素早く判断して行動に移れます。
3.備蓄や装備を適正に行う。

防災のためだけに備蓄や装備を準備するのはコストパフォーマンスも悪く、期限切れや故障、紛失などのメンテナンスも大変です。一方で日常の消耗品のみでは万一の際不足する可能性もあります。
日常的に使用するものを余分に在庫して、古いものから使用してゆく「ローリングストック」を中心に非常用トイレなど本当に緊急時のみ必要な防災グッズを備蓄するなど、効率的な備えを行いたいものです。日常で使うポットやウォーターサーバーなども日常と災害時と両方で使える仕様であると普段の備品がそのまま災害時のアイテムとして活用できるので効率的です。
企業の場合、細かな管理が煩わしい、コストパフォーマンスが悪いと感じる場合には、どういったものが必要で、どのように備えるべきかというものをアウトソースするのも一つの方法です。
4.なんのための防災かを考える。
防災グッズを備えたり、マイタイムラインを整備するのは、なんのためかというのを改めて考えてみましょう。大前提としては、自分の命、身を守るためですが、生活の基盤が失われては、たとえ命が助かったとしても次のステップに進めないこともあります。災害の規模によっても、すぐに日常に戻れるのか時間がかかるのかが変わってきます。
事前に想定していなかったり、準備が足りないと、万一の際にとれる選択肢が少なくなります。
災害など、非常時では、できることが制限されたり、対策が限定されることが多いですが、防災アイテムを備えたり、備蓄したり、家具の固定など事前の対策をすることで、万一の際に、選択肢を増やすことができます。
防災は、「万一の際の選択肢を増やすこと」をイメージして、マイタイムラインの設定、避難計画を立てると良いかもしれません。
一人で考えたり、自分たちだけで考える必要はないので、必要に応じて友人知人と相談したり、有識者や外部のコンサルタントに相談するのもよいでしょう。